
<Fariy Tale>
羽のついた少女、なにやら怪しげな道具を持つ老婆、大きな帽子とひげをつけた小柄な老父・・・。
鮮やかなカラーの絵がついた英字本は、30過ぎの男性が通勤途上に読むにふさわしくない。
相応に混んだ地下鉄の中、隣に立った若い男性が、不審そうにちらりちらりとこっちを見ている。
泉田は大きくため息をついた。
読みたくて読んでいるのではないのだ。別にファンタジーにのめりこもうとも思わない。
だが涼子とつきあっていると、実際にこういうものに出会ってしまうのだから仕方ない。
涼子は驚くほど、こういった超自然的なものについて博識だ。
泉田も少し知識をつけておかなければ、彼女の推理の手伝いが出来ない。
・・・しかし、妖精にはおとぎ話の中だけで活躍してほしいものだ。
泉田は心からそう願い、また本に目を落とした。
「まったく、あの刑事部長(オヤジ)ときたら、まるで妖怪ぬらりひょんよ。」
「はぁ・・・ぬらりひょん。」
今朝読んだ中には載っていなかった。あたりまえである。
『妖精図鑑』の中に日本の妖怪は入っていない。
「知らないの?日本の妖怪の総大将だとまで誤解されている妖怪なのよ。」
妖怪に総大将がいることも、しかもそれが誤解だということも知らない。
警部補という立場において、それを申し訳なく思うべきだろうか?
疑問は山のようにあるが、泉田は結局身についた社会人としての慣習で、頭を下げた。
「不勉強で申し訳ありません。」
「本当よ。知らない人がいない人がいるとは思わなかったわ。
ちなみにお由紀は冴えないルックスの座敷童子(ざしきわらし)ね。
あ、でもあれって居ついた先を裕福にしちゃうのか。それはちょっと違うな。他に何か・・・。」
「そういうのは疫病神でいいのよ。居ついた先に不幸をもたらす存在。
まさに日本警察にとってのあなたのようにね、お涼。」
参事官室の入口から凛と響く声、室町由紀子が立っている。
「出たわね、妖怪!ノックもなしに何の用よ!」
「開けっ放しで、しかも大声で上司の悪口をおっしゃっている方の扉を叩く方が無作法な気がしたのよ。
はい、これ。次の会議の資料よ。先に配られてたのに部屋に忘れていったでしょう。」
「捨てていったのよ。」
「「昼から使うんでしょう!?」」
しらっと言ってのける涼子に、泉田と由紀子の声が重なる。
「あ、失礼いたしました。」
「いえ、いいの。泉田警部補のご苦労はよくわかっているわ。がんばりましょうね。」
「はあ。」
涼子がきろっと由紀子を睨むが、由紀子はその視線をものともしない。
「じゃあお涼、遅れないようにね。」
「ふんっ。」
泉田は前を通り過ぎる由紀子を軽く敬礼で見送った。
由紀子は、一瞬微笑むと次の瞬間にはぴんと背筋を伸ばし部屋を出て行った。
「あ〜くやしいっ。なんかあいつにぴったりの妖怪はいないかなあ。
泉田クン、何か思いつかないの?」
「あいにく不勉強なもので。」
誰かを妖怪に例えるって、なんて難しいことなのだろう。
泉田は思わずため息と共に瞑目した。
「そんなこと言ってるから、いつまでたっても事件の謎がとけないのよ。ちょっとは勉強しようって思わないの?」
涼子はあきれ顔で、泉田を見つめている。
「警察に入ってからの試験には出なかったですけどね。」
あまりの言われように、泉田も言わなくて言い低次元の嫌味をこぼした。
ぴくり。
涼子の頬が動き、嫌味など言うものではないと瞬時に覚るが、もう遅い。
「・・・昼からの会議、キミが出てよね。」
「えっ!?」
昼からは溜まり溜まった書類の整理を終わらせる予定だったのに。
「あたしはもうあの妖怪ぬらりひょんの顔もお由紀の顔も見たくないの。妖怪に見えない人が見てちょうだい。
お昼に行ってくる。あ、会議は1時からだから。」
「え?あと15分じゃないですか!」
「そうよ。がんばってね。」
足音高く前を通る女王陛下に、泉田は空腹を抱えて敬礼した。
あと15分。携帯食料の予備はあっただろうか?
夕刻、泉田はぐったりと消耗して執務室に戻ると、
申し訳なさそうな顔をして帰っていく同僚たちを何とか笑顔で見送りながら、上着を脱いで大きなため息をついた。
あそこは確かに妖怪のたまり場だ。
誰もが皆己の保身と欲のために、ひしめきあっている。
「わかったでしょ?」
涼子が隣に立ち、資料を摘み上げる。
泉田もなんとか立ち上がって、涼子に向き直った。
「あ、ご報告が遅れて申し訳ありません。
内容自体は・・・今年に入ってからの未解決事件についての、その・・・責任のなすりつけあいで終わりましたが・・・。」
取り逃がした犯人を捕らえることこそが重要なのであって、誰が失敗したのか、その責任を誰が取るのか、その代役には誰がつくのか、
そんなことはどうでもいいだろう!と憤っていたのも、会議の途中まで。
延々と続くその手の話は泉田の常識を超える長さとくだらなさで、だんだんと自分が異世界に紛れ込んだ気になってきた。
「やっとあいつらが妖怪に見えた?」
「・・・少なくとも警視のご苦労の一端を垣間見ることが出来ました。」
涼子はぱさりと資料を置くと、満足げに微笑んだ。
「それでこそ行かせたかいがあったってもんよ。」
机の上に置いていた英字の妖精図鑑を手に取った涼子は、ぱらぱらと頁を繰る。
「一応勉強してるじゃない。」
「妖怪は載っていませんでしたが。」
泉田は苦笑しながら、涼子から本を受け取った。
「泉田クン、小さい頃妖怪とか妖精の本って読んでないの?」
「あまり・・・。」
化学の実験本や昆虫の図鑑の方がずっとおもしろかった。
思えば、文系人間になったのはつい最近のような気がする。
涼子にそう言うと、少し首をかしげてこう問いかけてきた。
「じゃあ『セントエルモの火』の話は知ってる?」
それは聞いたことがある。マストや船の舳先にともる青白い火のことだ。
「たしか静電気が原因の現象だったと思いますが・・・。」
「そう、怪現象の中では比較的明確に説明できるもののひとつよね。」
怪奇現象や妖怪・妖精の中には、
科学的に説明できる現象や、元になった生物がいる例が意外に多い。
中でも『セントエルモの火』は、20世紀以降も海原や高山でしばしば目撃されており、
人工的に発生させるのは困難だが、嵐や悪天候の後、先端の尖った部分に静電気が溜まり、
青白いコロナ状の放電を起こす現象であると明確に説明されている。
大海原、嵐にもまれた帆船のマストの先に揺れる炎。
幻想的な光景だ。
「怖がられていたでしょうけど、ロマンティックでもありますよね。」
泉田が少し遠い目をした。
涼子はその一瞬を見逃さず、満足げに微笑むと大きく頷いた。
「でしょ?じゃあ今年の休みはクルージング。セントエルモの火を見に行くわよ。」
「・・・は?」
「山は登るのが大変だから、やっぱり船かな。あの忌々しいアルゴ号みたいな大きさのものね。
木製よりは金属製の方が火は発生しやすそうだけど、もう少し条件については研究するわ。」
「あの・・・警視?」
「あたしが求めているのは、事実に基づいた浪漫なのよ。わかる?
「わかりません。」
即答。
わかってたまるものか。ましてや大海原にひっぱりだされるなんてとんでもない。
「あら?じゃあ残ってまたあの百鬼夜行の会議に出てくれるってことかしら?」
ぐっ。
泉田は返答に詰まった。
それは嫌だ。
「魑魅魍魎たちのわけのわからない低次元の怪談より、おとぎ話でしょ?それも浪漫たっぷりの。」
ぐっ。
泉田は再び返答に詰まった。
涼子がにっこりと笑う。
「決まりね。」
いつもの帰り道を、涼子は泉田に腕を預けて歩きだした。
夜風が心地いい。
「ドラよけお涼・・・か。」
ふいに泉田がつぶやいた。
涼子がぴくりと眉を上げた。
「目の前の上司を呼び捨てにするなんて、いい度胸じゃない?」
泉田は違う違うと手を振りながら、ため息混じりにつぶやいた。
「いや、決して他意あってのことではありません。でもドラキュラも避けて通るということは、
あの魑魅魍魎たちにも勝てるってことだと・・・今日そう思いました。伊達ではない異名ですね。」
「ぜんぜん誉められている気はしないわよ。」
涼子は軽く泉田の腕をつねった。
泉田は苦笑いしながら言った。
「つまり無敵だってことですよ。」
涼子は少し首をかしげて、そして花がほころぶように笑った。
「それはあたりまえじゃない?」
まだ時間の早い都心は人で溢れている。
その中を泳ぐように涼子と歩調を合わせて歩きながら、泉田は思った。
この人は、魔女かもしれない。
きっとあの魑魅魍魎、妖怪たちをしのぐ、とんでも怪物なのだろう。
でもこの人が上司でよかったと、時々思ってしまうのはなぜだろう。
「ねえ、何食べる?」
そんな気持ちを知ってか知らずか、
今も不思議を追いかけ、おとぎ話を紡ぐ最強の女主人公は、煌く星の瞳で、泉田を見上げた。
泉田は小さくため息をつきそして微笑んだ。
(END)
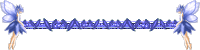
*そっか、薬師寺涼子の怪奇事件簿っておとぎ話だったんだ(違)。
官僚さんも大変だな〜と、全然前に進まない国会を見ていてふと書きたくなったお話でした。
いっそお涼みたいな政治家、インパクトあっていいかもしれないですね。
日本の末路はわかりませんが(特に外交)。その時には泉田クン、がんばって。